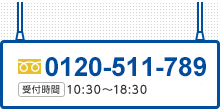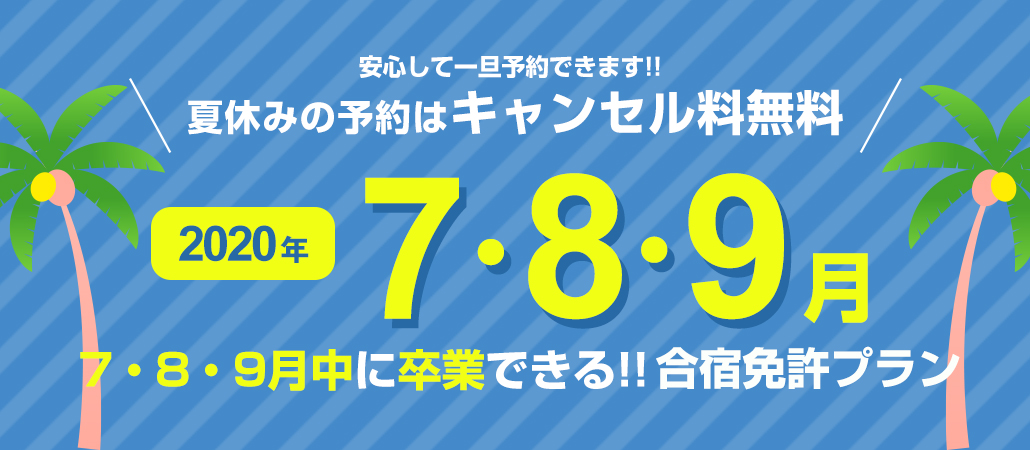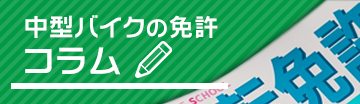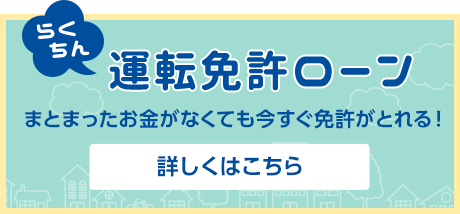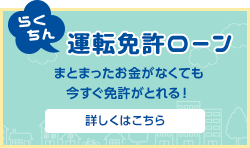中型免許は、トラックの運転などの仕事や、大型免許へのステップアップとして活躍する免許です。しかし、具体的にはどこまでの運転が可能なのか、ほかの免許とは何が違うかあまり知られていない免許でもあります。
ここでは「中型免許で運転できる車」と、その「取得方法」、さらに新しく誕生した「準中型免許」についても紹介します。中型免許で運転できる範囲と、主な使用例を確認しましょう。
中型免許を取得する条件
中型免許には6つの取得条件があります。以下の取得条件を満たしているか確認してみましょう。
1.必要な免許
中型免許を取得するためには、3種類の免許の中から、いずれかを取得している必要があります。
1つめの取得条件は、「普通免許」を取得していて、免許の取得から2年以上経過していることです。ただし免許停止期間がある場合は、その期間を除いて計算します。
2つめの取得条件は、「大型特殊免許」の所持です。こちらも免許取得時から免許停止期間を除いて、2年以上経過している必要があります。
3つめの取得条件は、「中型8トン限定免許」の所持です。中型8トン限定免許を所持している場合は、限定解除試験を受けることで、中型免許を取得することができます。
2.年齢
満20歳以上であること。
3.視力
両眼 の視力が0.8以上、片眼の視力が0.5以上であること。(眼鏡、コンタクトレンズの使用可)。深視力検査で、誤差が平均2㎝以下であること。
4.色彩識別
交通信号機の赤色・青色・黄色を識別できること。
5.聴力
10メートルの距離で90dbの警音器の音が聞こえること。(補聴器の使用可)
6.運動能力
自動車の運転に障害を及ぼす身体障害がないこと。
中型免許でどんな車が運転できる?人気が高いのはマイクロバス
1.中型免許で運転できる車種とは?
中型免許で運転できるのは、「車両総重量11トン未満で、最大積載量が6.5トン未満」の車両です。そして「乗車人数は30人未満」と定められています。
この条件に当てはまる人気の車種には、主に貨物の輸送に使用される「4トントラック」、そして乗客を運送する「マイクロバス」があげられます。普通自動車免許とは違い、中型免許で運転できる車両では、11人以上を乗せることが可能です。
そのため、幼稚園や老人ホームの送迎などの仕事や、プライベートでの大人数を乗せての旅行など、用途が広いことが特徴です。ほかにも、「第二種中型免許」を取得すれば、送迎以外にも、運賃を徴収して旅客を運ぶこともできます。
2.注意が必要な車種について
中型免許ではマイクロバスを運転できますが、2007年の法改正以前に取得した「中型8トン限定免許」は運転することができません。実は中型免許は2007年に新設された免許で、それ以前に取得された旧普通免許が「中型8トン限定免許」と呼ばれています。
この免許では「車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満」で、「11人未満」の車両しか運転できません。そのため、11人以上が乗れるサイズのマイクロバスは、運転することができないのです。
また、8トントラックは、「最大積載量が8トン」のトラックであるため、こちらも運転することができないので注意しておきましょう。8トントラックを運転する場合には大型免許が必要です。
中型免許を取得する方法
中型免許を取得するためには、8トン中型限定免許を持っているか、普通免許の取得から2年以上経過している必要があります。
どちらも自動車教習所で教習を受けることが一般的で、さらに合宿教習を受けることもできます。それぞれの取得方法をみてみましょう。
1.中型8トン限定免許を持っている場合
中型8トン限定免許を持っている場合は、限定解除試験を受けることができます。指定の教習所で受講してから、技能試験を受けることが一般的です。学科教習はなく、技能教習のみの受講です。
【教習例:友部自動車学校の場合】
・中型8トン限定免許を取得していることが条件
技能時間:5時限
費用:84,024円
年齢:満20歳以上
視力:両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上かつ深視力検査で2cm以下の方
※眼鏡・コンタクトレンズ使用可
このように限定解除なら、短期間で講習を終わらせ試験を受けることができます。次は普通免許を持っている場合の取得方法を確認しましょう。
2.普通免許を持っている場合
普通自動車免許を持っている場合も、教習所で講習を受けてから、試験を受けることになります。中型8トンの限定解除試験に比べ、学科講習があり、技能講習が多くなっています。
またAT免許を持っている場合は、さらに4時限程度の教習が追加されるため事前確認が必要です。
【教習例:友部自動車学校の場合】
※普通車MT免許を持っている場合
・普通免許、または大型特殊自動車免許を取得して2年以上経過していることが条件
技能時間:15時限
学科時間:1時限
費用:税込167,724円+仮免交付料2,800円=170,524円
年齢:満20歳以上
視力:両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上かつ深視力検査で2cm以下の方
※眼鏡・コンタクトレンズ使用可
③合宿教習の時間と費用
普通免許の取得では合宿教習が知られていますが、中型免許を取得する際も「合宿教習」を利用できる教習所が多くあります。短期間に集中することで、効率的に取得することが可能です。
【教習例:友部自動車学校の場合】
※最短合格の場合
| 8トン限定免許所持の合宿 |
日数:3泊4日 |
総額:127,000円 |
| 普通車MT免許所持の合宿 |
日数:8泊9日 |
総額:216,100円 |
教習所に通うほかにも、試験場で一発合格を目指すこともできます。ですが、中型免許では普通自動車以上に高度な技能を求められるため、教習なしで合格することは現実的ではありません。
あくまでも一度試験に合格したことがあって、免許を失効してしまった人のための制度と言えるでしょう。
準中型免許が誕生する

平成29年度3月12日から新しく「準中型免許」が設けられました。普通免許と中型免許の中間と言える免許です。この免許には以下のような特徴があります。
1.準中型免許の特徴
-
- 特徴1 普通免許を持っていなくても取得することができる
- 特徴2 18歳から免許取得が可能
- 特徴3 車両総重量は7.5未満で、最大積載量4.5トン未満
- 特徴4 11人未満まで乗車可能
中型免許は20歳以上で、普通免許の取得から2年経過していることが必要条件でした。しかし準中型免許は、このように「18歳以上」であれば、「普通免許を持っていなくても受験することが可能」です。
また、普通免許の上位免許なので、取得1年未満では準中型自動車の運転には初心者マークが必要ですが、普通自動車の運転には必要ありません。これだけだと分かりづらいので、ほかの免許との違いを表で確認してみましょう。
|
普通免許 |
準中型免許 |
中型免許 |
| 必要資格 |
満18歳以上 |
満18歳以上 |
満20歳以上
普通免許が必要 |
| 車両総重量 |
3.5トン未満 |
7.5トン未満 |
11トン未満 |
| 最大積載量 |
2トン未満 |
4.5トン未満 |
6.5トン未満 |
| 乗車定員 |
11人未満 |
11人未満 |
30人未満 |
このように、重量に関してはちょうど中間で、乗車できる人数は普通免許と変わりません。そのため、準中型免許で主に運転できる車両は、いわゆる2トントラックがメインになります。
主に小売店への商品運送や、宅配便の配達などに使用されている車種であるため、運送業に就くためには運転が必須と言えます。準中型免許なら、18歳以上で取得でき、2年以上と言う制約もないため、すぐにトラックを運転できることがメリットです。
中型免許とは違い、高校を卒業して、すぐに運送業の現場で活躍することができるようになります。こうした変化によって、運送業界の人で不足が解消されることが期待されています。
一方で、新しい普通免許では、車両総重量が5トンから3.5トンに引き下げられているので、新しく普通免許を取る人は注意が必要です。
2.準中型免許の教習
準中型免許は、普通免許を持っている場合は、準中型免許の教習のみを受けます。持っていない場合は、まず普通免許の教習を受け、その後に準中型免許の教習を受けることが一般的な流れです。
準中型免許の技能教習では、主に最大積載量2トン程度の小車格のトラックを利用して教習します。準中型車も合宿教習を利用できる教習所もあるので、探してみると良いでしょう。
【教習例:友部自動車学校の場合】
※普通車MT免許を持っていない場合
技能時間:41時限(普通車技能28時限+準中型技能13時限)
学科時間:27時限(普通車学科26時限+準中型学科1時限)
費用:税込368,664円+仮免交付料2,800円=371,464円
年齢:満18歳以上
視力:両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上かつ深視力検査で2cm以下の方
※眼鏡・コンタクトレンズ使用可
【教習例:友部自動車学校の場合】
※普通車MT免許を持っている場合
技能時間:13時限
学科時間:1時限
費用:税込156,924円+仮免交付料2,800円=159,724円
年齢:満18歳以上
視力:両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上かつ深視力検査で2cm以下の方
※眼鏡・コンタクトレンズ使用可
中型免許に関するQ&A
中型免許に関してよくある質問をまとめました。ぜひご一読ください。
Q.中型免許を履歴書に書くときはどのように書くのですか?
A.中型免許の正式名称は「中型自動車免許」です。そのため、履歴書には「中型自動車免許 取得」もしくは「中型自動車第一種運転免許 取得」と記載しましょう。中型8トン限定免許の場合は、「中型自動車運転免許(8t限定) 取得」もしくは「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と記載しましょう。
Q.中型第二種免許の取得条件は何ですか?
A.中型第二種免許の取得条件は、中型第一種免許と比べて、条件に2つの違いがあります。1つめは満21歳以上であることです。2つめは、他の第二種免許を取得しているか、普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかの第一種免許を取得してから、3年以上経過していることです。
Q.準中型免許にも第二種免許はあるのですか?
A.いいえ、準中型免許には第二種免許はありません。第二種免許があるのは、普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許、牽引免許の5種類です。
Q.大型免許の取得には、中型免許が必要ですか?
A.取得条件となる免許の1つですが、他にも取得条件になる免許があるので、必ずいるものではありません。中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していて、満21歳以上、免許停止期間を除いて3年以上経過していれば大型免許の取得試験を受けることができます。
Q.今から「中型8トン限定免許」を取得することはできますか?
A.中型8トン限定免許は、2007年6月以前に普通免許を取得した人への措置なので、新しく取得することはできません。新規で取得する方は、必要に応じて中型免許もしくは準中型免許を取得しましょう。
Q.中型免許の一発試験の合格率はどれぐらい低いのですか?
A.一発試験で合格することは大変困難であり、新規の取得の場合、合格率は数パーセント程度です。そのため、新規取得では教習所に通ったほうが良いでしょう。
中型免許・準中型免許を取得するなら教習所へ
中型免許は、普通免許と同様に合宿で免許を取れることもメリットです。そのため、これから運送に関係ある職業に就く予定のかたは早めに取得しておいた方がよいでしょう。
特に就職を控え、まとまった時間を取りやすい大学生は、合宿で免許を取得しておくことで、就職の幅を広げることができるはずです。
また、準中型免許も、18歳以上から取得できるため、普通免許を取得する延長上で取得することができます。そのため、高校を出てすぐに運送業に就く予定のかたには、必須の免許でしょう。さらに準中型免許を所持していれば、中型免許の教習の一部が免除されます。
そのため、中型免許のステップアップとしても有効な免許と言えるでしょう。免許の教習料金やスケジュールは教習所ごとに異なります。中型免許・準中型免許を取得したいかたは、早めに教習所に問い合わせておきましょう。
中型免許を取得するならコチラ

 平成29年度3月12日から新しく「準中型免許」が設けられました。普通免許と中型免許の中間と言える免許です。この免許には以下のような特徴があります。
平成29年度3月12日から新しく「準中型免許」が設けられました。普通免許と中型免許の中間と言える免許です。この免許には以下のような特徴があります。